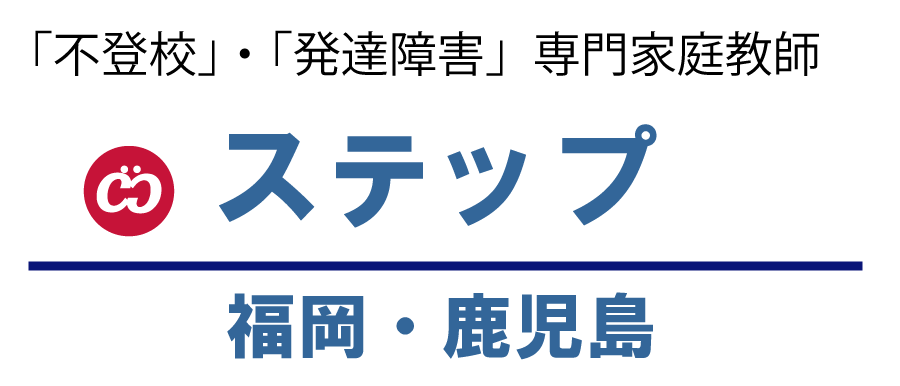【保存版】不登校の始まりに気づいたら読む記事|4段階のステップと親の対応法
「朝、どうしても起きられない…」
「学校に行きたくない…」
わが子からそんな言葉を聞くと、親としては胸が張り裂けそうな思いになりますよね。
「いったい何が原因なんだろう?」
「この先どうなってしまうんだろう?」
と、不安でいっぱいになるのは、当然のことです。
こんにちは。不登校と発達障害の専門家として、これまでたくさんの子どもたちと、そして保護者の皆さまと向き合ってきました。もし今、あなたがお子さんのことで深く悩んでいるのなら、どうか一人で抱え込まないでください。そして、焦らないでくださいね。
実は、不登校からの回復には、多くの子どもたちがたどる共通の道のりがあります。それは、「葛藤期」「受容期」「回復期」「再登校・社会参加期」という4つのステップです。
このステップを知っておくだけで、親であるあなたの心は少し軽くなるはずです。なぜなら、「今、子どもがどの段階にいるのか」が分かり、この先どう進んでいくのか、見通しを持つことができるからです。
今日は、この「不登校回復への4つのステップ」について、そして、それぞれの段階で親として何ができるのかを、優しくお話ししたいと思います。
ステップ1:葛藤期
「ゆっくり休んでいいんだよ」が一番のお薬
子どもが朝起きられなくなったり、腹痛などの体調不良を訴えたりして、学校を休み始めてから1週間ほど。この時期は、4つのステップのうち、最初の「葛藤期(かっとうき)」にあたります。
この時期、一番つらいのは、誰よりもお子さん本人です。「学校に行かなきゃいけないのに、行けない…」という、言葉にならない葛藤で心も体もエネルギーを使い果たし、疲れ切ってしまっています。
だからこそ、この時期の親の関わり方が、今後の回復への道のりで最も大切になります。
この時期に、保護者が心がけてほしいのは、たった一つ。「安心できる環境をつくること」です。
「なんで学校に行かないの?」
「何があったの?」
心配だからこそ、つい理由を聞きたくなってしまいますよね。でも、その質問が、お子さんをさらに追い詰めてしまうことがあります。
今は、何も聞かずに、ただ「ゆっくり休んでいいんだよ」と、お子さんの心と体を休ませてあげてください。あたたかい食事を用意して、静かに見守る。それだけで十分です。あなたが「味方でいるよ」というメッセージが、何よりのお薬になります。
ステップ2:受容期
葛藤期にゆっくりと心を休ませ、少しずつエネルギーが回復してくると、お子さんに小さな変化が見られるようになります。これが、2段階目の「受容期(じゅようき)」に入ったサインです。
「受容期」に入ったかも?と感じるサイン
⚫︎子どもから話しかけてくるようになる
⚫︎「ねぇ、このアニメ面白いよ」
⚫︎「今日の晩ごはん、何?」
など、他愛もない日常会話が増えます。
それは、お子さんの心が少しだけ外に向き始めた証拠です。
⚫︎ リビングで過ごす時間が増える
⚫︎ 自分の部屋にこもりがちだったのが、家族のいるリビングで食事をしたり、テレビを見たりするようになります。
こうしたサインが見られたら、「ああ、受容期に入ったんだな」と考えて良いでしょう。葛藤期に親がつくってくれた「安全基地」の中で、少しずつエネルギーが溜まってきた証拠です。
ただし、この時期はまだとてもデリケート。少しでもプレッシャーを感じると、すぐに葛藤期に逆戻りしてしまうこともあります。焦りは禁物です。
「受容期」の関わり方は、葛藤期の「静かに見守る」姿勢から、少しだけシフトチェンジが必要です。お子さんから話しかけてきたら、その会話を何よりも大切にしてください。
たとえそれが、あなたの聞きたい「学校のこと」や「将来のこと」でなくても、笑顔で耳を傾け、会話を楽しみましょう。このコミュニケーションの積み重ねが、お子さんの心をさらに元気にしてくれます。
「受容期」の子どもへの誘い方 - 心をひらく“黄金律”
「少し元気が出てきたみたいだし、どこか外に誘ってもいいのかな?」
そう考え始めるのも、この「受容"期」の頃かもしれません。はい、この時期からは、少しずつ社会とつながるためのトレーニングとして、散歩や買い物などに誘ってみることも可能になります。
でも、ここには一つ、とても大切な「誘い方のコツ」あります。誘い方を間違えると、お子さんの心を閉ざし、葛藤期に戻してしまうきっかけになりかねません。
例えば、次のAとB、どちらの誘い方が望ましいと思いますか?
* 誘い方A:「勉強の遅れが心配だから、一緒に本屋さんに行かない?」
* 誘い方B:「最近〇〇(子どもの好きなアニメ)の新しいグッズが出たらしいよ。今度、街に出たときに見に行ってみる?」
専門家の視点から見れば、答えは明確に「B」です。
誘い方Aは、「勉強の遅れ」という親の不安が先に立っています。勉強が苦痛で学校に行けなくなっているお子さんにとって、これは大きなプレッシャーです。親が勉強のことで焦る役割を担う必要はありません。
学習の再開については、私たちのような専門家と一緒に、お子さんのペースで進めていくのが最も安心な道です。
一方、誘い方Bは、お子さんの「好き」という気持ちが出発点になっています。
ここに、誘い方の“黄金律”があります。
* 黄金律①:子どもの「好き」から始めること
* 黄金律②:「~してみる?」と提案し、決定権は子どもに委ねること
* 黄金律③:目的は「本人が楽しむこと」。達成できなくてもOKとすること
「本屋」ではなく「好きなアニメグッズのお店」へ。「勉強」のためではなく「楽しいから」行く。この違いが、お子さんの心を動かすのです。
「もしよかったら、行ってみない?」と優しく提案し、もし「うーん、やめておく」と言われたら、「そっか、わかったよ」と、あっさり引きましょう。その繰り返しの中で、お子さん自身が「行ってみようかな」と思えるタイミングが必ず来ます。
その先にある「回復期」そして「社会参加」へ
受容期に、親子のあたたかいコミュニケーションと、楽しい経験を通してエネルギーを十分に充電できると、お子さんは自然と次の「回復期」へと進んでいきます。
自ら学習に意欲を見せ始めたり、外出の範囲が広がったり、友人と連絡を取るようになったり…。そうして、ゆっくりと「再登校・社会参加期」へとつながっていくのです。
不登校からの回復の道のりは、一直線ではありません。時には立ち止まったり、少し後戻りしたりすることもあります。でも、大丈夫。
あなたがこの4つのステップを心に留めておくだけで、お子さんの小さな「できた」に気づき、その成長を心から喜べるようになります。
そして何より、忘れないでください。お母さん、お父さんが笑顔でいてくれること、そして「あなたのことが大好きだよ」という気持ちで寄り添ってくれること。それこそが、お子さんにとって一番の安心基地であり、未来へ進むための、何よりの力になるのですから。
一人で頑張りすぎないでくださいね。いつでも、私たち専門家を頼ってください。一緒に、お子さんの未来を応援しています。
カテゴリー: 不登校について
投稿日:2025年08月20日