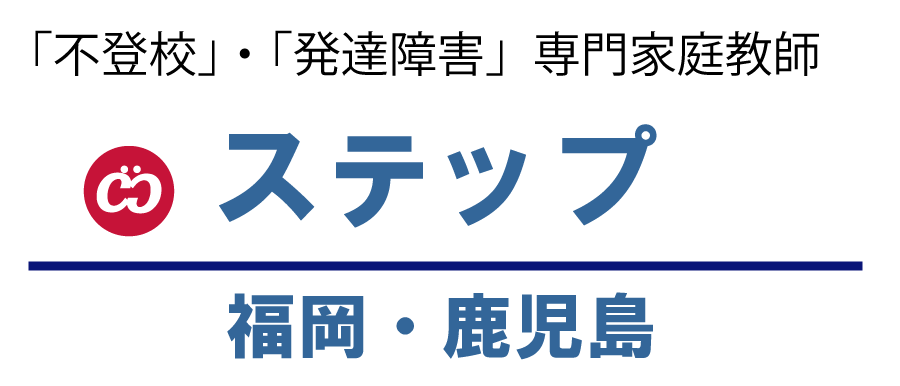【貧困と不登校】経済的な困難と不登校を抱える家庭に知ってほしい支援のカタチやん
近年、「無理に学校へ行かなくてもいい」という考えが広まり、不登校に対する世の中の見方は少しずつ変わってきました。心が弱っているときに、無理をする必要はありません。それは私たちも同じ考えです。
しかし、ただ「見守る」だけで不登校が解決するわけではありません。
実際の現場でサポートをしている私たちから見ても、適切なサポートの有無が子どもの未来を大きく左右していると感じます。
不登校と貧困は深く関係している
不登校の背景には、いじめや発達障害、親子関係などさまざまな理由があります。その中でも見過ごされがちなのが「家庭の経済状況」です。
貧困家庭では、子どもが不登校になったときに、
• 学習サポートを受ける余裕がない
• 心理的な支援にアクセスできない
• 進路の情報が手に入らない
といった壁が立ちはだかります。
結果として、不登校のまま中卒あるいは通信制高校を卒業しても、就職や自立が難しく、親の扶養から抜け出せない→貧困の連鎖というケースも多くあります。
宝物である子供たちがこのような理由で望む未来を得られないというのは、私たちにとってこのような現実は何より辛いことです。
では、どうしたらその悪循環から抜け出すことができるのでしょうか?
1. 情報を集めることから始めよう
まずは、支援の情報を集めることが第一歩です。
一人で抱え込まず、学校・地域の支援センター・民間の支援団体など、相談できる窓口は意外と多く存在します。
私たち「家庭教師ステップ」でも、無料相談を行っています。
2. できる範囲でサポートを受けよう
経済的に余裕がないと「支援なんて無理」と感じるかもしれませんが、全部を完璧にやろうとしなくていいのです。
できることから少しずつ始めてみるだけで、状況は変わっていきます。
特に注意したいのは、親も子も「どうせ無理」「うちにはできない」と思い込んでしまうこと。
この“負のループ”にハマってしまうと、前に進む気力すら失ってしまいます。
誰かの力を借りることは、決して甘えではありません。
むしろ、「前に進もうとしている証拠」です。
3. “つながり”を諦めないで
貧困や不登校の状況にあると、社会から孤立したように感じることもあります。
でも、人とのつながりを持ち続けることが何より大切です。
・同じ悩みを持つ親の会
・支援団体のSNSやLINE登録
・地域のボランティアや居場所づくりの団体
今は、ネットを通じて少しの勇気で多くのつながりを得られる時代です。
孤立さえしなければ、きっと道は開けます。私たちも、子どもたちとご家庭の“伴走者”でありたいと願っています。
不登校や貧困は、一つひとつの家庭に深刻な影響を与えます。
でも、「何かできることはないか?」と考えるその気持ちが、未来を動かす原動力になります。
誰にも相談できずにいる方は、どうか一度、私たちにご相談ください。
一緒に、小さな一歩から始めていきましょう。
#不登校 #貧困家庭 #教育格差 #発達障害支援 #学校に行けない #子どもの貧困 #家庭教育サポート #中卒からの進路 #通信制高校 #子どもの未来を守る #不登校専門家庭教師ステップ #発達障害専門家庭教師ステップ #鹿児島
カテゴリー: 不登校について
投稿日:2025年04月02日