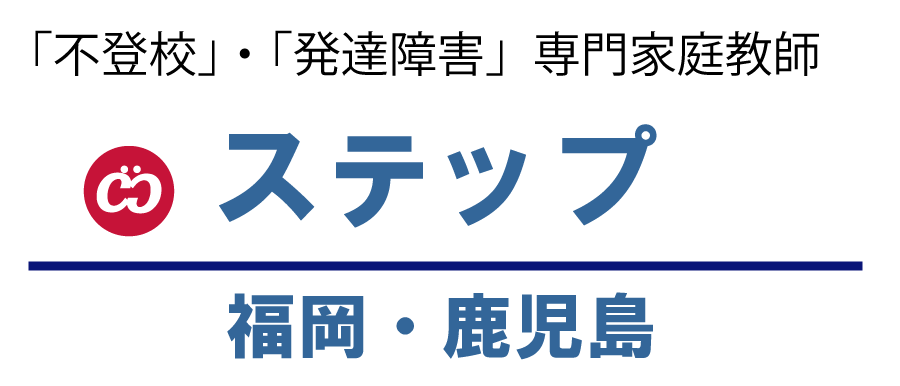不登校から「ひきこもり」へ──お子さんを孤立させないために、いま親ができること
お子さんの不登校が続くと、
「このままずっと学校に戻れなかったらどうしよう」
「将来、社会に出られなくなってしまうのでは…」
と、不安を感じる保護者の方は多いのではないでしょうか。
その不安は決して大げさではありません。
私たちが日々支援の現場で感じるのは、
“学校に行けない時間”が長くなるほど、社会とのつながりを取り戻すことが難しくなるという現実です。
1. 支援が途切れると、孤立が深まる
不登校の子どものうち、3人に1人以上が学校や支援機関とつながっていないといわれています。
相談先が見つからず、家庭内で悩みを抱えたまま時間だけが過ぎてしまう──
そうしたケースが増えています。
そして、その結果として「ひきこもり」に移行してしまう例も少なくありません。
全国では約146万人がひきこもり状態にあり、
その半数以上(50.9%)が不登校の経験を持っています。
早い段階で支援とつながることが、
お子さんの未来を守るための第一歩なのです。
2. 「学校に戻すこと」=ゴールではなく、“再出発”のための第一歩
以前は「学校に戻すこと」が最終目標とされてきました。
しかし、私たちステップでは、実際の生徒たちの進路や将来を見つめる中で、
学校復帰・社会復帰の“タイミング”と“準備”こそが重要だと感じています。
調査書や進路状況などを考慮すると、
できるだけ早い段階で学校に戻る、または社会と接点を持つことが、
将来の選択肢を広げることにつながります。
一方で、心の準備が整わないまま戻っても、
再び不安が大きくなり、元に戻ってしまうこともあります。
だからこそ私たちは、
「心の回復」と「現実的な一歩」を両立させながら、
お子さんが安心して再出発できるようサポートしています。
3. 社会復帰の厳しい現実
最新の調査によると、
不登校を経験した子どもが将来正社員として働いている割合はわずか9.3%。
パート・アルバイトが32.1%、そして**「どちらでもない(無職や不明)」が18.2%**という結果でした。
つまり、約半数が安定した職に就けていないという厳しい現実があります。
不登校の問題は、単なる“学校生活の悩み”ではなく、
将来の社会参加に深く関わる課題でもあるのです。
だからこそ、早い段階で「社会に戻る力」を育てることが欠かせません。
4. ステップが大切にしている4つのサポート
① 安心できる「居場所」をつくる
先生が訪問する時間は、プレッシャーも評価もない“安心の時間”。
心が落ち着く環境の中で、お子さんが少しずつ前を向けるようになります。
② 「心の回復」と「行動」を同時に支える
気持ちの整理を大切にしながら、
学校への連絡、登校練習、家庭学習の再開など、
現実的なステップも一緒に進めていきます。
③ 「小さな社会とのつながり」を取り戻す
家庭教師との対話や学びは、
お子さんが社会と再びつながるためのリハビリです。
「話せる人がいる」という安心が、次の行動の原動力になります。
④ 卒業後も続く「伴走型サポート」
中学・高校を卒業したあとも、進学・就職といった次のステージに向けて支援を継続。
さらに、在籍生・卒業生を対象に、インターンシップや就労体験など、社会で生きるための実践的なサポートも行っています。
社会に出る力を少しずつ育て、孤立しない未来づくりを目指します。
5. ご家庭だけで抱え込まないでください
不登校は、お子さんの心からのSOSです。
そして、そのSOSを受け止めるご家族にも大きな不安と負担がかかります。
「どうしたらいいか分からない」
「このままで大丈夫なのか不安」
そう感じたときこそ、支援を始めるタイミングです。
ステップは、お子さんとご家族に寄り添いながら、
“心の回復”と“社会への再出発”を全力でサポートします。
どうか、一人で抱え込まないでください。
その一歩が、お子さんの未来を大きく変えます✨
カテゴリー: 不登校について
投稿日:2025年10月27日