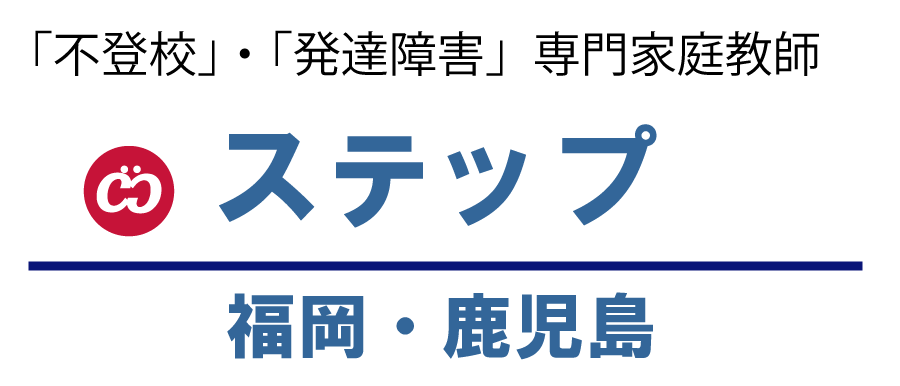不登校や発達に課題がある子どもたちの大学受験【小論文編】
大学入試で「小論文」が必要だと聞くたびに、「うちの子に、いったい何が書けるのかしら…」と、お母様の胸に不安がよぎることはありませんか?
近年、総合型選抜(旧AO入試)などで小論文を課す大学は増える一方。避けて通れないとは分かっていても、そのハードルの高さにため息が出てしまうお気持ち、私たちは痛いほどよく分かります。
どうして「書けない」の? 理由はお子様の“特性”にあります
そもそも、なぜお子様たちは小論文に強い苦手意識を持ってしまうのでしょうか。
それは決して、やる気がないからではありません。
• 世の中の出来事に、興味を持つ「きっかけ」が掴みにくい
• ニュースや社会問題と言われても、自分とは遠い世界に感じてしまい、何から考えたらいいか分からなくなってしまう。
• 「何を書けばいいの?」情報整理がちょっぴり苦手
• 頭の中に色々な考えが浮かんでも、それを言葉にして、順序だてて並べる作業に混乱してしまう。
• 「自由に書いていいよ」がかえってプレッシャーに
• 答えが一つではない課題に対し、「正解」を探そうとしてペンが固まってしまう。
そんなお子様の姿を見て、「どう声をかけたらいいのか…」とお母様ご自身も悩んでしまいますよね。
ご安心ください。ステップは“いきなり書かせません”
だからこそ私たちは、書かせる前の“対話”を何よりも大切にしています。
「小論文の授業」と聞くと、難しいテーマについてひたすら書く練習を想像されるかもしれません。でも、ステップの時間は全く違います。
① まずは先生との「おしゃべり」から
例えば「AI社会」というテーマでも、まずは「最近、どんなことでAIって使われていると思う?」といった身近な質問から始めます。
先生が上手に質問を重ねるうちに、最初は黙っていたお子様も、ぽつりぽつりと自分の考えや感じたことを言葉にし始めます。この「おしゃべり」こそが、すべての土台です。
② 「言葉のタネ」を一緒に見つけて、並べます
対話の中で見つかった「言葉のタネ」を、「じゃあ、この順番で話してみようか」と先生が一緒に整理し、構成を組み立てます。「結論→理由→具体例」といった型が見えるだけで、お子様の表情はパッと明るくなり、書くことへの不安が「書けそうかも」という自信に変わっていきます。
③ ペンが止まっても、一人にはしません
もし途中で分からなくなっても、大丈夫。担当講師が隣で「こんな言葉はどうかな?」「伝えたかったのは、こういうこと?」と一緒に言葉を探し、お子様の“言いたい気持ち”を形にするお手伝いをします。
「書けた!」の自信が、お子様の未来を拓きます
小論文が書けるようになることは、単に受験を乗り越えるための技術ではありません。
• 自分の気持ちを、言葉で整理する力
• 相手に「伝えたい」ことを、届ける力
• 自分と社会とのつながりを見つける視点
これらはすべて、お子様がこれから社会で生きていく上で、かけがえのない“お守り”となる力です。
「うちの子が、こんなにしっかりした意見を持っていたなんて」。
そう言って、お子様の書いた文章を嬉そうに読んでいらっしゃるお母様の姿を、私たちは何度も見てきました。
最後に
「やっぱり、うちの子には無理かもしれない…」。
そう感じてしまう日もあると思います。でも、どんなお子様にも、その子だけのユニークな視点と「言葉の芽」が必ず眠っています。
私たちステップは、その小さな芽を見つけ、お子様自身の力で花開かせるお手伝いをします。
大学受験はゴールではありません。お子様が自信を持って次のステージへ進むための、大切な一歩です。まずはお母様の不安な気持ちを、私たちに聞かせてください。
お子様と一緒に、確かな一歩(ステップ)を踏み出しましょう。
カテゴリー: 不登校、発達障がいの受験情報
投稿日:2025年10月02日